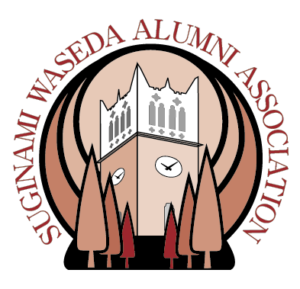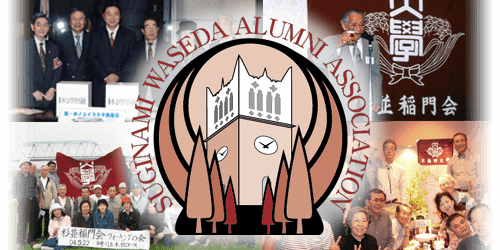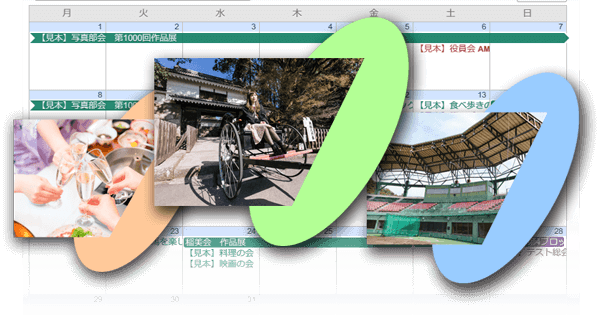190607 6月7日(金) 第6ブロック 東京湾一周クルージングのご案内
~ 初夏の海風に吹かれ、豪華船で征く ~
乗船予定の大型豪華船(シンフォニー)は日の出桟橋を正午に出港し、レインボーブリッジをくぐり、東京湾に出ます。東京タワー、東京ゲートブリッジ、羽田空港、大井ふ頭など、海から見る大都会、東京は全く違う顔を私たちに見せます。そこは非日常の世界が広がります。
全行程は2時間10分、ゆっくりとランチ(和洋、豊富なメニュー。飲み放題)を楽しみながら、東京湾の名所を巡ります。
是非この機会にご家族、ご友人を誘ってご参加ください。
開催日:2019年6月7日(金) (雨天決行)
募集人数:35名 (*定員に達し次第、締め切ります)
料金:9,500円
集合場所:日の出ふ頭、シンフォニー乗り場(待合室)
集合時間:11時30分 (時間厳守、11時45分には乗船)
申込期限:5月30日(木) (*期限後の取り消しはキャンセル料が発生します。)
(現地までの交通) 新橋 (ゆりかもめ線で3駅) ➡ 「日の出」駅下車、徒歩1分。改札出たら右
〇 新宿(大江戸線)➡ 汐留(ゆりかもめ線で2駅)➡ 「日の出」駅
申し込み先(第6ブロック世話人)
迫田泰尚 : (mail) yyyyy-sakota-123@docomo.ne.jp (Tel) 090-2714-9988
影井恭子 : indigo-blue@nethome.ne.jp 090-9133-6064
190330 3月30日(土)第6ブロック 花見&昼食開催
各地で桜の開花宣言が続く中、18人が井の頭線西永福駅に集合。
曇り空で些か寒く感じる天候ではあったが、大宮八幡宮を経て善福寺川沿いを散策。桜の名所の尾崎橋~天王橋界隈も満開には今少しの状況ながら、各人ゆったりとした歩みで春の雰囲気を堪能した。
集合写真の撮影後、阿佐ヶ谷方面に向かい和食レストラン「かごの屋」にて昼食。 「花冷え」を楽しく感じさせる半日でした。
(参加者)久保田貞雄、中村昌代、熊谷彰、宇都木光一、戸川達次、中山廣文、加藤健、川島格、西島宏志、影井恭子、下川典子、栗原健、野嵜正興、竹内元義、清水克祐、松崎仁紀、迫田泰尚、久留島正和
【写真/川島格、文/久留島】

181208 12月8日(土) 第6ブロック 年末懇親会開催
2018年の世相を1字で表す「今年の漢字」(日本漢字能力検定協会)は「災」だが、紀平梨花さんや藤井聡太君などフレッシュな16歳が日本の前途を明るくしてくれる。 紀平さんがカナダ・バンクーバーで世界一に輝いた12月8日(土)夜6時、第6ブロックの年末懇親会がダイニングバー「クルーズ吉祥寺」で開宴した。
久留島正和世話人代表は「忘年」という概念が好みでないようで「年末懇親会」とおっしゃる。川島格さんが集合写真に苦労された小さな店だから、借切りで皆さんにマイクを廻し甲論乙駁して頂く構想だったのが、ゲストの久保田貞雄会長と中村昌代さん(1B)を加えて出席17名ではお店に申し訳ない…と貸切を解いたので、マイクなしの論談は聴覚劣化のこの耳には鮮やかに届かない。 新しい年号、スポーツ界の明暗、日産・ルノー、北方領土…何が話題か解らないが、ワイワイガヤガヤの2時間は瞬く間に過ぎ、杉並稲門会の高齢者たちは至って健やかだと気分が好い。 来2019年の漢字は「幸」とか「福」でありたい。
【参加者17名(敬称略・地区順)久保田貞雄、中村昌代、栗原健、松崎仁紀、竹内元義、野村修、清水克祐、山中治樹、山中正子、田中重、荻野慶人、久留島正和、下川典子、加藤健、川島格、迫田泰尚、影井恭子】
(荻野慶人・写真/川島格)

181124 11月24日(土) 第6ブロック主催「両国界隈散策」開催
今回で8回目となる第6ブロック恒例の下町散策は、両国界隈を巡った。
両国散策は、昨年11月3日に実施したが、この時は両国駅の南側だったので、今回は北側を巡った。午前9時半に19名が両国駅に集合。昨年同様、案内役の金子健治さん(台東稲門会)からコースの説明を受けたあと、駅をスタート。旧安田庭園~刀剣博物館~NTTドコモ歴史展示館~慰霊堂~復興記念館~相撲部屋(八角部屋&錦戸部屋)~野見宿禰(のみのすくね)神社~すみだ北斎美術館などを巡ったあと、江戸東京博物館にて記念撮影。そのあと、同館内7Fの食事処「桜茶寮」にて昼食をとる。食事の後、解散とし、各自、館内を見学して帰路についた。
参加者(敬称略順不同)
加藤健、清水克祐、井上樹彦・倫子、中村昌代、早川敏清、千葉明義、竹田隆雄、 金子守、内田直彦、宇都木光一、前田研二、平澤光郎、阿部正、板垣伸夫、影井恭子、 久留島正和・規子、川島格 計19名
(文&写真) 川島 格

180721 7月21日(土) 第6ブロック「新会員歓迎&懇親会」開催
猛暑の続く中、吉祥寺第1ホテル「Park Street」にて総勢19名の参加で開催。
堀川皓之助さん(1951年法卒)の乾杯の音頭で始まり、和洋のバイキング形式の食事を楽しみながら歓談。 出席された4人の新会員の皆さんは、既にスポーツ観戦の会、Walkingの会、写真部会、美術クラブ等に入会、 活動を開始しており、自己紹介でも各々の巾広い趣味が披露されました。
その後、加藤健幹事長の杉並稲門会関連の説明、井上さんや西島さんのご挨拶もあり、和やかな雰囲気の中で終了。いつもの荻野さん(1955年文卒)の一本締めでした。新会員の皆さんの積極的な活動に期待したいと思います。
参加者(敬称略) 荻野慶人、元重英治、川島格、影井恭子、下川典子、加藤健、栗原健、野嵜正興、勝島敏明、竹内元義、 清水克祐、西島宏志、井上樹彦、堀川皓之助、●山中治樹、●山中正子、●松崎仁紀、●迫田泰尚 久留島正和
●印は、新会員
(文;久留島、写真;川島)

山中 正子さん

松崎さん

いつものメンバー

堀川さん、迫田さん、荻野さん、山中さん

記念撮影